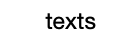土のかたち
校舎のはずれの一番低い所にその教室はありました。正直なところややきの引ける面持ちで階段を下りた覚えがあります。ずっと終わりのない作業が続く“絵を描く”ということに言い知れぬ重苦しさを感じ、苛立ちに戸惑っていたからです。逃げるように降りた階段の先にあったのが、ヤキモノです。
図らずも全くの偶然ではありましたが、ヤキモノのとの出会いは極めて幸運な出来事でした。回転に合わせて形が手の中から現れ、すぐ目の前に存在する、ロクロに出会ったとき、「モノ」を作る喜びをもう一度感じることができました。
その後数年間、ロクロを用いた制作を続けることになるのですが、「焼物だったら茶碗を作ればいいんじゃないか、その方が意味がある。」などと思い込んでいました。しかし思い返せば茶碗や壷の姿ではなく、ロクロの上で立ち上がる土を見たいがために、器物の形を借りていたのに過ぎなかったのです。
そうなると「自分のもの」はという思いが頭をもたげ始めるのも当然のことといえます。
しばしば良く挽けたと思っていた碗の形に一筋のひび、割れ目が入っていることがありました。技術が未熟なわけですから非常に良く割れるのは致し方のないことでありますが、出来上がりへの期待と同じだけ大きな落胆がありました。仕事場の隅に積み上げておいた割れてしまったカケラを眺めるうちに、回転に合わせて出来上がった、滑らかな表面と、断面の放つ鋭い表情に目を奪われていました。そこには自らの手で作られた形と、手では作り得ない形が共存していたのです。
この破片をちょとしたいたずらの気持ちで、載っけたり、差し込んだりと組み合わせてみました。これがロクロを基本としたパーツを組み上げる仕事のはじまりです。
この一連の仕事を続ける上で、ロクロを使って形づくられた土(粘土)を、まず制作の基になる材料として認識している自分に気づくことになりました。例えば、材木店で買ってきたベニヤ板や、あるいは石材店から仕入れた御影石や、鉄材店から搬入されたコールテン鋼といたような、これから加工されるであろう材料と同じように、自らの手で、同心円状の形態をした粘土を材料として用意するということです。なぜこのような面倒な作業が必要かというと、土(粘土)というものは、どのような形態にもなるもので、つまりはその固有の形を持っていないものなのです。このえたいの知れないものを自分に引き寄せてくるための手続きとしてまずロクロで形を作る。土(粘土)にある形を与えるためには極めて合理的なものです。
このように土(粘土)とロクロの関係を対象化して考えることがえることができるようになると、もうひとつ大切なことが見えてきます。これまで土(粘土)を材料と述べてきたように、土(粘土)が素材として存在するのではなく、ヤキモノつまりは、焼かれて硬くなるもの、形づくられ、加工され、表面処理され、高温加熱され定着されるもの、その過程全体を含めたものを素材として用いているということです。
さまざまな形に分割、切断された土(粘土)のパーツを選び出し組み合わせる作業の中には、一定の方向性というか、判断の拠り所とでもいうべきものがつねに介在しています。形を決定すること、形に色を与えて結果を待つこと、窯から出てきた仕上がりを受け止めること。そこにのみ意識の入り込む隙間があるように思われます。誤解を恐れずに言うならば、ヤキモノという仕事は、非常に物に即した行為ではないかと考えています。逆に物に寄り添うことなしに、またその論理に近づくことなくしては成立しないといえます。
破片を発見することによって認識することができた、自己と物の関係をもう一度確認してみようと考えたのが今回の仕事です。今まで使い慣れたロクロから離れて、土(粘土)を自分に引き寄せることができるのか、または近づいていくことになるのか、破片を使うことなく、立ち上げられた形に、もうひとつの形を組み合わせるだけのぎりぎりの要素に絞り込むころによって、見えてくるものは何か、抑制された表面から現れるもの何か、これらを探る試みなのです。
この展覧会の会期を終えるころには少しは次の仕事につながる結果が見えてくるはずです。手で触れることのできる現実の物が持っている広い世界の一端でも現れていればと。
1995.08 ギャラリーコヤナギ 個展リーフレット